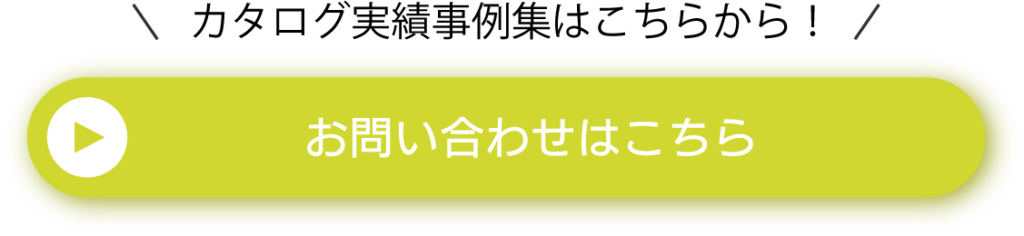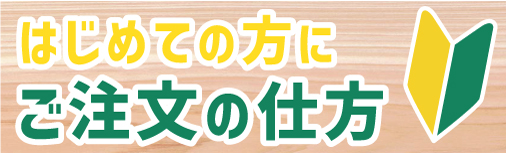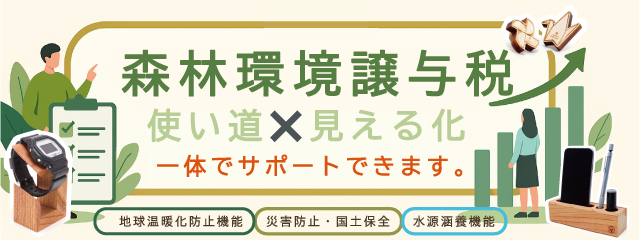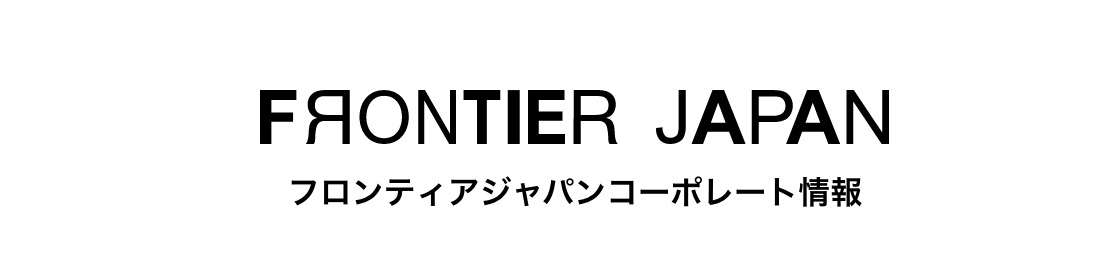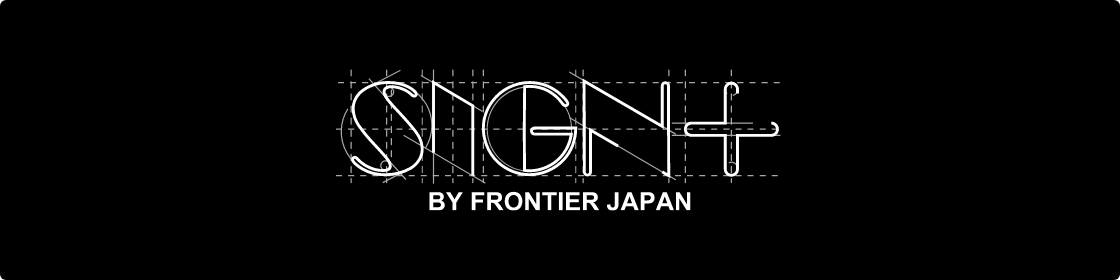年末年始は、ブランドが一年の感謝を“形”にして届ける季節です。最近ですと、中身の見える福袋をはじめ、年末年始商戦にはこの数年変化が見られます。
また、世界的な流行病や人材不足などの問題もあって社会的に年末年始は休もうぜ?と、年末年始はデパートや百貨店、ショッピングセンターなどはお休みというところも増えてきています。
今回は、とくにアパレルのちょっとハイブランド向けに、いうても年末年始って書き入れ時ではあるから、それなりに販促とかキャンペーン仕掛けたいんだよね。というニーズにお応えするサスティナブルなノベルティのおすすめを紹介していきます。
その前提としては、リアル店舗はお休みだから、ECで配布しやすい、軽くて同梱しても負担にならない。香りなどが染み付いたりしにくいアイテムを、環境経営のことをあれこれと書いてそれなりに評判のコラム担当なかの人1号が紹介していきます。
さて、ここ数年でアパレル業界のノベルティはちょっと変わってきています。
これまでの量をベースにしたノベルティ「どれだけ配るか」よりも、「どんな想いを込めて贈るか」が問われてきています。
そんな人の心を動かすのは、値引きでも数量でもなく――ブランド体験。
ギフトとしてのノベルティを渡す、使うその“瞬間”が、世界観を伝える最初のメディアになれるかどうか?そこを書いていきます。
年末年始商戦のノベルティは「ギフト+ブランド体験」の勝負
年末年始!その特別なシーズンが、アパレルのお客様を行動させたッ!!
はい、年末年始のアパレル業界はなんといっても“数字が動く”特別な時期です。
どれだけの数字が動くのか?
それは、SC販売統計調査報告をもとにすると、2024年12月の全国ショッピングセンター売上は前年同月比+5.3%。
特に都市部の大型商業施設では+9.5%と高い伸びを記録しています。
消費データブックをもとに考えると、日常着や普段着では大きな変化はそこまででもないですが、おしゃれ着や高級ブランドアパレルでは顕著な伸びがみられるようです。
引用:SC販売統計調査報告 2024年12月
https://www.jcsc.or.jp/cat_press/p_20250127_110473
引用:消費データブック(2025/3/10 号)
https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20250310_024963.pdf
それもそのはず、この時期は冬のボーナス、セール、帰省や初詣といった外出機会や人との接触機会が重なり、購買心理は「機能性」から「気分を上げたい」「誰かに見せたい」へと切り替わ流ためと言われています。
新規のお客様の心を掴むブランド体験ノベルティとは?
そして、この時期にはおしゃれ着や特別な一着を求めて、はじめてブランドに触れる。というご新規さまも増える時期です。
この新規を掴めるタイミングで重要になるのが、ギフトとブランド体験の両立になります。
おしゃれ着や「特別な一着」を探す流れの中で、これまで一度もそのブランドに触れていなかった人が
はじめて商品ページを開いたり、店舗に立ち寄ったり、SNSでフォローする。
といった“最初の接点”が生まれます。
ここで配るものを、ただの販促ノベルティをプレゼントしているのと、
「素晴らしい!ブランドの精神が形になったようだ」と感じるノベルティをプレゼントしているのとでは、
最初の接点のインパクトのある印象が特別なものになるかどうかの分かれ道となりそうです。
おまけのノベルティ?世界観のノベルティ?
この時期の新規流入は、普段の広告獲得と少し違うということを踏まえて、この時期のノベルティを考えていきます。
まず、年末年始に入ってくる新規は「とりあえず安いから買いたい」というよりも、次の心理が強く働く新規のお客様が相対的に増えるとされています。
「せっかくの年末年始だし、ちょっと良いもので”いいね!”と誰かにいわれたい。」
「ちゃんとしたブランドのものを持ちたい」
こういった“背伸び心理”で購入されるといっても過言ではないと思います。
だからこそ、”一見さん”と軽く扱わず、ノベルティやギフトを通じて、ブランドの世界観を感じられる設計が重要になります。
ブランドの世界観や価値観そのものに触れるのがほぼ初めてだからこそ、初回のタッチポイントの設計から、購入を通じたブランド体験が良いものかどうか?がダイレクトに次の一着を買うか?買わないか?を決めてしまいます。
もちろん、接客や発送などすべてが問われますが、このタイミングで渡すノベルティには、単なる”おまけ”ではなく、もっとブランドを体現するというとちょっと言い過ぎですが、そういう世界観
伝えることが求められます。
ノベルティを通じて「このブランドを選んでよかった。」と思っていただけるかどうかのほんの少しの差。
これがけっこう大事。ということは、販促やマーケティングをされていればご理解いただけると思います。
とくに、ハイブランドのアイテムにおいては、価格競争ではなく“共感競争”に移行しているこの時代。
年末年始商戦だから、価格を下げたり、クーポンを発行したりで新規の方を集めるのも一手ではありますが、どれだけ心に残る“贈り方”をデザインできるか?
共感であつめることができるかどうか?これが年末年始商戦のノベルティ、成功の分岐点と思っています。
アパレルブランドが選ぶノベルティとして“サステナブルな贈り物”
年末年始のノベルティに限らずですが、近年もっとも注目を集めているキーワードが「サステナブル」です。
サスティナブルは、ESG経営だとか、脱炭素ではTCFDとしてだったりで企業経営に小さくない影響をもっていて、もはや一時のトレンドではなく、取り組みがブランドの“信頼の証”として機能するようになってきました。
ただ、ここ数年でアパレル業界ギフトやノベルティの文脈では、ちょっとした変化があります。
それは「環境に配慮している」から、「環境と調和している」へのシフトです。
「環境配慮」と「環境調和」のちがい
環境配慮は、環境に気を付けていて単純に消費電力を抑えます。自然の再生可能エネルギーにします。といった、いうなら行動量のこと。それをたくさんしている量で評価してください。というもの
環境調和は、ブランドのなりたちや作っている素材に関わる環境配慮。自然や文化の中でブランドそのものが“共に生きるあり方”ともいえます。
日本の縫製技術を継承します。というブランドや、魚網の再生素材などを利用したブランド、トラックの幌をアップサイクルしてバッグにしたりといったブランドと、その商品に配慮が浸透しているブランドが共感をベースに強いファンマーケティングを展開しています。
もちろん、いま、ブランドとしてそういった取り組みをされていなくとも、ノベルティを通じて環境調和を届けることは可能です。
ノベルティに調和の世界観を
素材・形・伝え方に「思想」を宿せば、ノベルティそのものが“その哲学を触って感じる体験”となります。
そんな調和的なサステナブルノベルティを考えるうえで大事なのは、素材の話よりも、理念といえます。
“調和しているブランド”のノベルティは、それ自体が小さなメッセージボトルのように、ブランドの世界観を静かに、けれど確かに伝えていけるかどうかが問われます。
最近では当たり前になりつつある「環境対応を頑張っている」ではなく、お、このノベルティ、そこまで考えているんだ。と“調和の思想そのものに共感するファン”を増やせるようにノベルティ選びを見直してみませんか?
年末年始におすすめのサステナブルで調和するノベルティ
先にも書きましたが「サステナブル」を掲げるブランドはとっても増えました。
もはやサスティナブルは、差別化の要素ではなく前提となっている。と言っても過言ではないと思います。
サスティナブルであることを強引に伝えると、ちょっと嫌われるといいますか、押しつけ感が出てしまいブランドイメージの毀損になったりもします。
とてもうまくやっているブランド、とくに環境に調和的なブランドほど、その“サステナブル”を行動ではなく体験として伝える傾向があります。
ノベルティでそれを応用すると、素材が環境にやさしいだけではなく、受け取った瞬間にブランドの哲学が伝わるような仕掛けを持っているように文脈として設計するのが良さそうです。
ノベルティを「ブランド文脈」で活かす方法
実は、結構、この時期は、ノベルティで新規のお客様を集めるのは戦略的にもやりやすいタイミングではあるんです。
というのも、年末年始の時期は、会社も休みになり、クリスマスも終わり、ちょっと時間を持て余す人が増える時期。
映画やYoutubeなどのコンテンツ、ゲームや読書をするということはあってもセカンドスクリーンでスマホやSNSに触れながらという人も多いです。
というわけで、というとあれですが、セカンドスクリーン狙いで、映画やYoutubeなどの広告枠、SNS広告のキャンペーンで、こういう自然の取り組みのノベルティを訴求するだけでも結構効果的だと思います。
ただ、もちろん普通にSNSでとやっても、ブランドの文脈に合わなければあまり意味はありません。
ブランド文脈に合わせるノベルティの作り方
文脈に合わせるなんて、ちょっとこ難し胃ことを言っていますが、大切なのは、ノベルティを「語るもの」にすることです。
それには“そのブランドらしさ”がどんな物語で伝わるのかを、あらかじめ意識しておく必要があります。
たとえば——
素材の背景を、ブランドの物語で語る。
「この木は、〇〇の間伐材を使っています。」という説明的な表現ではなく、「私たちは、森を未来に繋ぐ選択として、〇〇の間伐材を選びました。」という、”なぜ”を伝えるブランドに沿った文章にするだけでも、受け取る印象はまるで違ってきます。ちょっと言い過ぎかもしれませんがブランドの思想を感じさせる導線となります。
ノベルティの役割を“アフターブランド体験”にする。
渡したあとで世界観にふれるアフターブランドの体験をつくるには「受け取ったあとに、どんな瞬間に思い出してもらいたいか?」を起点に考えるのがおすすめです。香りや触れる感触など、五感から伝えることができるかどうかがポイントになります。ノベルティが“語らないメッセージ”として静かにブランドを伝えてくれます。
広告や投稿も“贈り物のように”演出する。
キャンペーン告知を“販売促進”として〇〇円以上購入でプレゼントと出すより、「感謝を込めて」という語りのトーンで提示して、感謝の範囲を人から社会や環境に広げていって“調和のノベルティ”であることが伝わるとその印象は優しくまとまります。ノベルティそのものが“調和のメッセージ”として機能するようになります。
サスティナブル調和のノベルティおすすめ5選
ここまでの内容を踏まえて、アパレル、ハイブランド向けの環境配慮や環境調和としておすすめのノベルティを紹介していきます。
くすのきカンフルブロック
自然の力でやさしく衣服を守ります。ハンガーにかけておくだけでくすのきの香りとブランドロゴが優しく語りかけてきます。
くすのきアロマチャーム
くすのきのもつ自然の力で衣類を守ります。こちらは、自由に形を切ってグッズにできるので、ブランドロゴやシンボルなどにあわせてオリジナルでつくれます。香りと見た目と自然の調和で訴求するならこれがおすすめ
組み立てプチカビン
飾るインテリアとしておすすめのプチ花瓶。間伐材はもちろん産地指定の木材でつくることもできます。例えば、ですが、ブランドで〇〇県にある縫製工場などをつかっていれば、その県の木をつかって地域全体のサスティナブルに。などの訴求も可能です。
蓋付きタンブラー
一見するとプラスチックタンブラーですが、木の端材やおがくずを51%混ぜてつくる木のサスティナブルタンブラーです。こちらも産地指定や支給材でつくれます。展示会のブースなどで木を使っていればその木をつかってつくるなども可能です。(塗料や接着剤が付着していると難しい場合がありますので、その場合は事前にお問い合わせください。)
ポーチ (Wood Cloth)
調和のノベルティとしてはこれが欠かせません。木の繊維を布地に織り交ぜてつくるポーチです。縫製も日本国内で行うため、間伐材を用いて環境配慮というだけでなく、縫製加工などを未来に繋ぐという調和も生み出します。
まとめ|2025-26年、販促の調和の想いが伝わるエコノベルティ
アパレル業界の販促は確実に転換点を迎えています。
価格やキャンペーンでの一時的な集客も大事ですが、「どんな想いを込めて届けているか」が購買理由にもなってきているような、購入の動機が移り変わる時代といえます。
そんな共感の消費が如実に合わられてきている2025年末年始のノベルティ戦略も、その流れを汲めるかどうかが問われています。
“ギフトとして喜ばれる”ことだけではなく、“ブランドの世界観を感じてもらう体験”としての価値が伝わるか
とくにアパレル関連では、サステナブルを「行動」ではなく「調和」として捉える企業が伸びていることもあるので、このあたりは私がああだこうだと書かなくとも、心で理解されている方が多いのかなと思っています。
ノベルティもまた、その調和の文脈の中にある小さなメディアです。
受け取った人の暮らしの中でふと手に取られ、香りや手ざわり、形や言葉で世界観を思い出してもらえるもの。
もちろん、当たり前のように環境配慮になっている。
そんな“語らないブランド体験”が、これからの時代の販促にふさわしい在り方といえます。
エコノベルティとは、環境にやさしいだけではなく、人の心にやさしく残るもの。
それをどうデザインするかが、次の時代のブランド価値を決めていくのかもしれません。
大量消費、大量配布のばらまきの時代から、適量生産、適量配布の環境調和の選択へ、
“ひとつひとつを丁寧に贈る”
それが、2026年に向けた販促の新しいスタンダードといっても過言ではないかもしれません。
では、最後までお読みいただきありがとうございました。
【ショールームのご案内】
フロンティアジャパンにて作成してきたノベルティアイテム、記念品はもちろん、最新商品や大型アイテムなど実績サンプルを多数展示してます。
木製品特有の年月とともに変わる風合い、味わい、木の種類による違いなどお手に触れて確かめられます。
なお、見学をご希望の場合は、お問い合わせフォームよりご予約いただけますと幸いです。
事例集カタログダウンロード